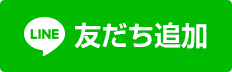初心者も簡単!扇子キットの基本的な作り方

夏の必需品である扇子の作り方を早速紹介していきたいと思います。1番簡単なのは扇子キットを使用しての作り方ではないでしょうか?
扇子キットでの作り方は初心者のかたでも挑戦しやすいです。まず、扇子キットで作る際の材料を説明致します。
- 扇骨(扇子の骨の部分)
- 竹串
- のり
- せめ(扇子の帯)
- 輪ゴム2本
- 地紙(扇子の絵柄がつく部分)
これらを使用して作っていきます。それでは順を追って説明します。
まず、折れた地紙を開いて左から3番目の折り目から1つ飛ばしで竹串を刺してください。この際、全9か所に刺す際に竹串が地紙の上から見えるくらいまで突き刺します。
9か所すべて終わったらジャバラ折でつけた折り目で畳んでいってください。畳むときには、開けた穴を縦に大きく開くように広げます。
扇骨の1つずつが重ならないように開き、段差のある部分まで糊を塗ってください。そして、左手に地紙を折りたたんだ状態で持ち、先ほど開けた穴へ扇骨を入れます。
全部入りましたら、扇骨を縦にし、糊がついてる段差の部分までゆっくり入れてくだい。拭き終わりましたら、畳んで輪ゴムで地紙の部分を
固定し10~20分ほど乾かします。
糊が乾いたら開いて、扇骨の1番外側の骨に地紙の分だけ糊付けし、地紙に貼りつけます。そして、また輪ゴムで固定をして乾かしていきます。
地紙からはみ出している扇骨をニッパー等で切除して、せめを嵌めて完成です!
作り方は以上でしたが、簡単に作れそうですよね。ちなみに扇子キットは、絵柄をつけるだけの作り方のものなら通販で200円ほどから販売しているので簡単に始められます。
この機会にオリジナルの扇子を作ってみてはいかがでしょうか?
様々な素材でできる扇子の作り方10選

先ほどは扇子キットでの作り方の紹介でした。扇子キットでの作り方は扇子を作るうえで基本となる作り方です。
それでは、他の素材で扇子を作ってみたらどういう作り方になるのでしょうか。オリジナルの扇子を作成しようとするとき、意外と様々な作り方があります。
今回は10通りの作り方を紹介いたします。
- 折り紙と割りばし
- クリアファイル
- 牛乳パック
- 100均の扇子(布張替)
- 100均の扇子(転写シール)
- 壊れた扇子のリメイク
- 田楽串とコピー用紙
- 厚紙
- チラシ 10.ハンカチ
では、それぞれの作り方を見ていきましょう!
様々な素材でできる扇子の作り方①:折り紙と割りばし
お子様向けの扇子です。折り紙をなにかに見立てて作ってみたりしたら面白いかもしれませんね。
材料はこちらです。
- おりがみ3枚
- A3サイズ画用紙
- 割りばし
- はさみ
- のり
- セロハンテープ
- 輪ゴム
まず、画用紙の上に折り紙を置き、折り紙の周りに1~2cmほど余裕を持たせて画用紙を切っていきます。その上に折り紙を張っていきます。
扇子にイラスト等をつけたい方はこのタイミングで描いてください。描けたら最初は谷折りからジャバラ折をしていきます。
端までジャバラ折が終わりましたら、畳んでいる状態で半分に折り、のりでくっつけます。割りばしを割って、1本ずつにテープをつけてください。
先ほどの画用紙の糊付けしてない端に割り箸を貼り付けます。そして、割りばしと割りばしを輪ゴムで留めたら完成です!
こちらは身近にあるものだけで作れる作り方で、穴を開けたりする必要もないので子供でもつくれます。
様々な素材でできる扇子の作り方②:クリアファイル
材料はこちらです。
- A4クリアファイル1枚
- ボタン1個
- ヘアゴム
- 油性ペン
- 穴あけパンチ
- 定規
- カッター
まず、A4ファイルを横向きに置き、縦が20.5cm、横が5cm間隔の長方形を6枚、油性ペンで線をつけていきます。そして、上から5cmのところから1番下の、左右から1.5cm空けたところまでカッターで傷をつけていきます。
扇子に絵柄をつけたい場合はここで描きましょう。クリアファイルのツルツルじゃない内側に描くと絵柄が剥げにくいのでおすすめです。
油性ペンで描いた線で切っていきます。そして、カッターで傷つけた左側の折線を山折り、右側を谷折りにして下から見たときにN字になるようにします。
下に少し隙間をあけ、穴あけパンチで1枚1枚穴を開けていきます。そしてカットしたクリアファイルの1枚目の右側と2枚目の左側を重ねていきます、これを全て繰り返してください。
全て重なりましたら、ゴムをくっつけたボタンを穴あけパンチで開けた穴に通します。これで完成です。
クリアファイルで作る扇子は透明感があるため、見るだけでも涼しげなので夏にはおすすめです。
様々な素材でできる扇子の作り方③:牛乳パック
- 1L牛乳パック2個
- タコ糸50cm
- 直径5mmのボルト1個
- ナット1個
- ワッシャー2個
- はさみ
- 穴あけパンチ
- ホチキス
材料は以上です。次に作り方を説明いたします。
牛乳パックを開いて19cm×3.5cmの大きさのものを16枚つくります。そして切ったもの全ての両端に穴あけパンチで穴を開けてください。
16枚全て重ねて片方の穴から、ワッシャーを通したボルトを差し込み、ワッシャーとナットでとめます。その状態で広げ、1番下の穴にタコ糸を通し結びます。
結んだタコ糸を2枚目の穴に通し、糸が崩れないようにホチキスで留めてください。これを全てに繰り返していき最後の穴に到達したらまた結び、完成です!
こちらはエコな扇子で、夏休みの工作等にも合うのではないでしょうか。
様々な素材でできる扇子の作り方④:100均の扇子(布張替)
- 布
- ボンド
- スティックのり
- はさみ
材料は以上です。次に作り方を説明いたします。
型紙に合わせて生地を用意します。ボンドを水で溶かし、生地をそこにくぐらせてください。
全体をくぐらせたら自然乾燥をさせてアイロンをかけます。できましたら生地の裏側に型紙通りに印をつけ、印より1cmほど大きめにはさみでカットします。
扇子の間隔に合わせてジャバラ折にしていき、下の余分な部分を切り取ってください。扇骨の1番外側のうちの1本にスティックのりを型紙通りにつけた印の部分に合わせて貼りつけていきます。
次に他の骨1本1本にスティックのりをつけ、ジャバラ折の山折りの部分に貼りつけてください。そして、最後の1番外側の扇骨に貼りつける前に、余分な生地をカットです。
全てに糊付けが終わったら輪ゴムでとめて乾燥させます。乾燥しましたら1度開いてみて扇骨の上ぎりぎりで余分な生地をカットし、完成です。
持っていた扇子の柄を気軽に変えてみたいときはこの方法を試してみてください!
様々な素材でできる扇子の作り方⑤:100均の扇子(転写シール)
- 無地の扇子
- アイロン転写紙
- あて布
- アイロン
- プリンタ
材料は以上です。次に作り方を説明します。
何も描かれていない無地の扇子を用意してください。アイロン転写紙に印刷する絵柄をパソコンで反転させ準備し、プリンターで転写紙に印刷します。
印刷後、インクが乾いたころに余白をとって切り取ります。そして転写前に扇子にアイロンを低温でかけしわを伸ばしておいてください。
しわを伸ばした扇子の上に切り取った転写シールを乗せ、約10秒ずつアイロンを押し当ててください。熱が冷めてから丁寧に転写紙をはがしていきます。
剥がし終わったら、あて布をしてもう1度アイロンをかけ、半日ほど置いておきましたら完成です!
もしもシールがはがれてきてしまったら、もう1度アイロンしたらくっつきます。絵柄を反転させて印刷することが少々手間にはなりますが、写真やイラストで作れるのでおすすめです。。
様々な素材でできる扇子の作り方⑥:壊れた扇子のリメイク
- 壊れた扇子
- コピー用紙
- のり
- はさみ
材料は以上です。次に作り方を説明します。
扇子を分解し、中骨(外側じゃない部分の骨)5本と親骨(1番外側の骨)だけ取っておきます。すべて骨のくびれの部分でカットします。
カットできましたら留め具で7本すべて留めてください。そうしましたら、次に型紙をつくります。
カットした骨の先端からの半円と、骨の中心部分からの半円を描きます。用紙から切り取り、16等分のじゃばら折をしてください。
1番左の折り目のみ切り取ります。そして、1番外側になった部分の裏側に糊付けをし隣にくっつけ、乾いたら扇骨に貼りつけていきます。
貼りつけ終わったら乾燥させてください。これで完成です。
お気に入りの扇子を壊してしまった場合、リメイクすることでまた利用できるのは嬉しいですよね!
様々な素材でできる扇子の作り方⑦:田楽串とコピー用紙
材料はこちらです。
- 田楽串
- コピー用紙
- はりがね
- ラジオペンチ
- ボンド
コピー用紙を横半分に折り、右側をさらに半分に折ります。そして1番右側の線の1番下から斜め45度に折ります。
そこを中心にどんどんジャバラに折り目をつけていき、余った部分と、高さを揃えるために上の部分をカットです。
下の部分は、用紙を半分の高さよりも少し下にずらしたところで、ここもカットしてください。広げて、もう1枚同じ大きさの用紙を作ります。
田楽串の上4cmくらいにボンドを塗り、ジャバラ折した用紙の1番端から順に1つ飛ばしで串を貼り付けていきます。ボンドが乾くのを待っている間に先ほどつくったもう1枚の用紙に絵柄をつけてください。
そして先に田楽串とくっつけた用紙のほうにボンドをぬり、絵柄のついている用紙を貼り付けます。そして再度用紙に折り目をつけます。
次にラジオペンチで針金を必要な長さにきって端を丸めてください。田楽串の隙間に針金を通し、串の厚みに合わせて反対側も丸めます。
新しい田楽串を2本準備して、片側にボンドを塗り、先ほどの針金のすぐ上から貼り付けます。乾くまで輪ゴムで固定をして完成です。
こちらも穴を開ける必要がなく、田楽串が和風な雰囲気を醸しだしてくれます。もしも家に田楽串がありましたら挑戦してみてください。
様々な素材でできる扇子の作り方⑧:厚紙
- 厚紙
- リボン等の飾り
- ボンド
材料は以上です。次に作り方を説明します。
厚紙をニンジンのような扇子の形に6枚切り取ります。そして1本ずつに好みの絵柄を付けていきます。
1枚1枚を少しずつ重ねてボンドで貼りつけ完成です。
厚紙で作ることで仰いだ時の風はほかの物よりも力強く感じる作品となっております。
様々な素材でできる扇子の作り方⑨:チラシ
- チラシ
- 両面テープ
- ペン
- はさみ
材料は以上です。次に作り方を説明します。
まずチラシで骨を5本作ります。適当なチラシを選び巻いて棒状にし、巻けたら両面テープで固定して下さい。
作った骨を上から圧っし、平たくします。次に扇子の地紙の部分を作成していきます。
地紙の型紙を生地二枚にペンで写してください。生地を切り取ります。
型紙と生地を合わせた状態で右端から順に折っていくのを二枚とも行ってください。生地の高さの分だけチラシで作った骨(いちばん右端の骨のみ片面、それ以外の骨は両面)に両面テープで張り合わせていきます。
表になる地紙の左端に両面テープを貼って裏側の地紙に貼り合わせてください。左端のみ貼り合わせたら、先ほど作っておいた骨を地紙の左端からひとつ飛ばしで貼り付けていきます。
骨をつけたところから順に、地紙に直接両面テープを貼り、表裏の地紙を貼り合わせます。全体を貼り終わりましたら扇子を開き、五本の骨が重なる部分に千枚通しやキリで穴を開けてください。
開けた穴に留め具をつけ、扇子の折り目をつけ直して完成です!棒状にして平たくする時にきつめに作らないと骨がゆるくなってしまうので注意が必要です。
様々な素材でできる扇子の作り方⑩:ハンカチ
- ハンカチ
- 洗濯のり
- 扇骨
材料は以上です。
このコラムで紹介した扇子の作り方④の布張り替えと同じ要領でハンカチを準備していきます。こちらのハンカチは布よりも厚さが薄いものが多いのでボンドではなく洗濯のりを原液で使用してください。
ボンドでやってしまうとハンカチがパリッとせず、蛇腹折りしにくくなってしまいます。ですので、ハンカチで扇子を作る際には洗濯のりで作ることがおすすめです。
割りばしで作る扇子の作り方

- 画用紙
- 輪ゴム三本
- 画用紙
- はさみ
- 定規
- コンパス
- 鉛筆
- 両面テープ
- のり
- 折り紙
材料は以上です。次に作り方を説明します。
まず、割りばし3本を輪ゴムで固定し、開きいてください。そのままでは閉じてしまうので、箸と箸の間もバツの形になるように輪ゴムで留めます。
割りばしを画用紙に乗せて割り箸よりも少し大きめにコンパスで型を二枚とり、切り取ります。
そして、画用紙一枚ずつに、折り紙を貼り付けてください。折り紙を貼り付け終わりましたら、両面テープで箸を画用紙側につけてください。
固定が終わりましたら箸と箸の間の画用紙部分にも両面テープを貼り、もう一枚の画用紙と折り紙を上から重ねます。余分な部分を切り取って完成です!
ジャバラ折は省いているので折りたたむことはできませんが、扇子の役割はきちんとこなしてくれる使用勝手の良い作品です。
画用紙で作る扇子の作り方

- 画用紙(縦10cm横9cm)
- 折り紙2枚
- カッター
- ぺん
- コンパス
- ボンド
材料は以上です。次に作り方を説明します。
まず、画用紙に1cm間隔で横にカッターで薄く線をひいていきます。その線でジャバラ折をしていきます。折り終わりましたら、1番上にきているところの上から4.5cmのところに扇子のくびれ部分を描いてください。
描いたくびれ部分を定規とカッターで切って、折り目でもひとつひとつ作っていきます。折り紙にコンパスで外側は半径8cm、半径4cmの半円を描き、線で切っていきます。
折り紙を上1cm、下0.5cmの幅でジャバラ折をしていきます。その折り紙に先ほど画用紙でつくった骨の部分をボンドではりつけ乾かしていきます。
乾いたら折りたたみ、穴開けパンチで骨部分の下0.4cmのところに穴をあけ、筒状にした画用紙をボンドでくっつけます。乾いたら完成です。
すべて紙でできており、軽くて可愛らしい扇子になります!
おすすめの手作り扇子キット


おすすめするのは、こちらの商品です。さきほど様々な素材でできる扇子⑤で紹介したような商品で、パソコンで絵柄をシールに印刷し、貼りつけるだけで完成するものです。
また、サイズ感も、畳んだ時に約22cmの長さで扱いやすくなっております。お値段もお手頃ですので、オリジナルの扇子を作りたい初心者の方には特におすすめです。
まとめ

様々な扇子の作り方を紹介してきましたが、これならできるというものも有ったのではないでしょうか。夏の必需品の扇子がオリジナルのものなら愛着もわきますよね。
簡単なものもあるので、是非挑戦してみてはいかがでしょうか。